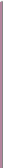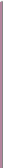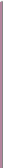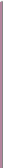|
4. おわりに
実験の結果, 今回試作した高齢者用コミュニケーション杖について, まだ多くの検討課題もあることが分
かった.
単体としては
1. 高齢者が転倒したとき, AM, FM のすべての帯域に対して警告を発信できないか.
|
| → | 小型化を含めて, いま, その技術的方法について検討中である.<
/font> |
|
|
2. 高齢者がコミュニケーション杖を使用中, 転倒したときと, 横にして置いたときとどう
区別するか.
|
| → |
1案として, 手で持つ部分に温度センサを取り付け, 把握部の温度を計測してそのデータ
を使用する.
2案として, 力を計測できる歪みゲージを張り付け, 把握部を力を計測する.
3案では, 単にスイッチを設ける. (3 案が一番可能性が高い.) |
|
|
3. デザイン, 材質, 重量などについては, 1 つ 1 つ解決を図って行く.
|
また, システムでは
1. GPS について,起動して,探索を開始し,自動位置追跡を行うための安定状態になるまでに時間(約
10分)がかかる.
|
| → | 安定状態になるまで NiCd 電池の替わりに容量の大きい鉛蓄電池を
使用する.
安定状態に達したあとは NiCd 電池を使用することになる. |
|
|
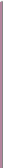
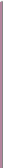 |
|
2. GPS の形状・重量が大きすぎる.
|
| → | 現在, GPS の電子回路の集積化が図られており, 数年後には
GPS の電子回路部分が腕時計サイズの寸法になると考えられる.
(これは併せて電池の重量・寿命の問題と上記 1.の問題も解決できる.) |
|
|
3. データ転送ユニットから無線で安定して転送できる距離が電波法で最大でも 500m程度であり, せっ
かくの GPS システムの能力を発揮できる範囲が現状ではあまりに少ない. (表 3, 図 2 に実際の位置計測
の結果を参考までに示した. 図 2 の SAITO のマークが高齢者の位置を示している.)
|
| → | 現在の NTT ドコモのシステムを本システムの一部に組み込むこと
で国内規模で探索ができるようになる. |
|
その他
1. コミュニケーション杖がアルミニウムでできているため使用時の落雷の危険性も新たに出てくる.
|
| → | 杖の材質の変更などを検討したり, 使用の制限を法的に定めてゆく. |
|
|
2. コミュニケーション杖を乱暴に扱っても, 壊れないこと.
|
| → | コミュニケーション杖とすべての電子回路の一体化を図る.
以上, 各種の問題点と解決手段を列挙したが, 現在, これらの各事項の可否について技術的な詳細検討を進めている最中である. |
|
|