 | |

| JAM SESSION |
| STAGE 2 |
 |
|
<伊藤> じゃあ, 何軒かで使おう, 5軒だったら4万ずつでいいわけでしょ. 又貸ししてもいいですかって聞いたら, 「伊藤さんが全部責任持つのならいいです.」 という具合に話がとんとんと進んで, その後いろいろ面倒なこともあったけれど, ともかくこの場所を 5 年間使おうという人が集まって, 建物も修繕して橦木館ができるわけです. <佐々木> 建築の設計事務所と, ギャラリーと, 演劇をやっている住み込みの管理人さん, 高橋先生と伊藤さんですね. <伊藤> そうです. 入ってすぐの洋館の一階は, 最初からギャラリーにしたかったんですね. それでさらに喫茶店にしてもらうんです. そうでないと, 門からふらりと人が入って来る口実がなくなるんですよね. そして奥の日本家屋のほうに管理人が居て, この部屋が高橋先生と僕の部屋で, 年中開いていてどなたも使っていただけるようになってる. 後で庭にあるお茶室も使えるように修復しました. 文化財だとか何とかで教育委員会にいろいろいわれましたが. <佐々木> この建物, 市の方で何か認定されているのですか. <伊藤> 名古屋市の文化財です. だから演劇を座敷でやるとかいうとうるさく言われる. 僕たちは使いたいように使っていますが. でも, 実はこの部屋の全部の部材が柾目なんですよ. 本当に. <佐々木> 本当に?今まで気にしてなかった. すごいですね. <伊藤> この障子知ってます?これね, 地獄組みと言ったかな, 縦横が編むように組んである. これは柾目のいい材料でないとできない細工. しかも面取りしてあるんです. 死ぬような仕事してるなと思う. だから, 悪い言い方すると, この建物つくった人は, 俺はこんな金持ちでこんなに凄いこと知ってて作ってるんだぞということ言いたいみたい. でも見た目は, きらびやかでなく凄く質素ですよね. <佐々木> そもそもこの建物はいつ頃建ったものですか. 住居として建てられたものですよね. <伊藤> そうです. ものすごく分かり易くいうと, 大正期に名古屋の陶器商が建てた. ここに棟札があるんだけど, 大正 14 年 10 月5日と書いてある. こっちが洋館ので昭和2年です. 洋館は, 陶磁器のバイヤーに住まわせたんです. |
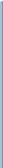 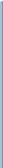 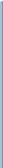 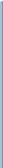 |
<伊藤> 2階がビリヤード室とトランプ室で, 寝室が1つあって, バストイレが付いてて, 下がダイニングとリビングみたいになっている. いまギャラリーになっているところです. それでこっちの日本家屋の方は, いまでも大家さんは離れと呼んでます. 番頭は離れの敷居が跨げなかった, という世界だったらしいです. <佐々木> 私も時々寄せてもらったりしますが, この場所は個人的な集まりや, 様々なイベントが開かれたり, いろいろ使われていますが, それは, 基本的には個人的なネットワークでつながっているものがほとんどの様でしたが, でも一昨年は少しオフィシャルにと言うか, 名古屋市の主催した世界都市景観会議に関連させて対外的なイベントも行われましたね. あれはやっぱり市の方から協力要請があったわけですか. <伊藤> ええ, ありました. かっこいい話としていえば, 建築遺産を生かした街づくりというテーマの格好の実例になるわけです. 歴史と文化みたいなことを街の中に残す必要がある, というのは僕も賛成したいと思います. でも本音を言うと, 僕は建物を残すということが大事なんじゃなくて, そういうものを起点にしてもう一遍文化をわれわれが作っていくことの方が大事じゃないかと思っているんです. 建物を残そうとすると, 一番の問題は経済的な問題です. ここの敷地は 600 坪ある. 今でも坪 150 万ぐらいだから9億円なんですよ. これが1人の人の相続税にかかってくるとしたら, とっても大変だし, 分割して地権者をふやすとまたいろいろ大変. そういった現実問題に対する手だてがやっぱり何もできていないのです. <佐々木> 保存を可能にするような公的な方法がないわけですよね. だから残すには公的な機関が一括で買い上げるしかない. あるいは大きな企業が買ってメセナとして開放するかだけれど. この近くにも幾つかありますが, 経済状況によって手放されたり, 管理されなくなったりと, 保証がない. <伊藤> だから歴史的な建物を活かそうと奇麗ごとを言ってはいますが, やっぱり5年で切って, 5年先になくなるというのは, みんなが要らないからなくなるというふうに理解しようと思ってます. 無理やり残して例えば放っておかれるより, もう建物は消えてしまったんだけど, たった5年間だけど名古屋に橦木館というのがあったということを誰かがずっと覚えていてくれれば, それでいいじゃないかっていう結論は持ってます. |