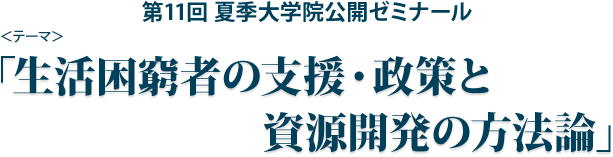
第10回のテーマが、「生活困窮者の支援・政策と社会福祉研究の視点」でした。政策上いったい誰を対象にしているのか、どの福祉行政組織で対応するのか、などの問いから出発しました。一回の大学院ゼミナールでは解けない課題が多く、第11回においても、視点をさらに発展させながら、このテーマを継続することとします。この新たな制度において、問題の解決を目指す、いわゆる出口プログラムづくりが予算制約の面から脆弱であることが指摘されています。そこで、今回のゼミナールにおいて発展させる視点は、出口プログラム資源の開発、入口の自立相談支援と出口プログラムとの接合をテーマに設定します。前回のテーマにおいて、この支援は、福祉行政組織のみの対応で解決できるのか、という問いかけをすでに行っていました。その意味では、民間組織との連携なしには実現しない課題であり、とりわけ社会的孤立の問題への接近と解決には、地域社会の協力・参加も必要となります。社会福祉制度は、対象を明確にすることが困難な「社会的孤立」にどこまで接近できるのか、社会包摂的政策の課題が指摘されてから15年が経過するなかで、その政策課題を出口プログラムの資源開発の方法論から考えます。
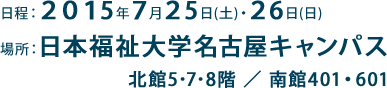
1日目【7月25日(土)】
基調講演 |
|||
| 「生活困窮者支援・政策が目指す資源開発 -社会的包摂の政策化過程の分析を踏まえて」 |
|||
|---|---|---|---|
| 古都 賢一 | 独立行政法人国立病院機構副理事長 (前 厚生労働省 大臣官房審議官) 日本福祉大学客員教授 |
||
シンポジウム |
「 生活困窮者支援における資源開発の方法 -実践からの普遍化」 |
||
| 日置 真世 | よりそいホットライン全国コーディネーター・ 日本福祉大学アジア福祉社会開発研究センター客員研究所員 |
||
| 朝比奈 ミカ | 千葉県中核地域生活支援センターがじゅまる所長 | ||
| コーディネーター | 平野 隆之 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | |
研究者の語り |
|||
| 「私の行ってきた研究とその方法 -生活構造論から地域福祉研究へ」 |
|||
| 野口 定久 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | ||
2日目【7月26日(日)】
分科会 |
A「量的研究(調査)法への誘い; “問い”の立て方から分析まで」 |
||
|---|---|---|---|
| 斉藤 雅茂 | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 | ||
| B「質的研究(調査)法への誘い -質的研究で実践現場のリアルが見えてくるⅡ-」 |
|||
| 田中千枝子 | 日本福祉大学スーパービジョン研究センター長・ 社会福祉学部教授 |
||
| 山内 哲也 | 社会福祉法人武蔵野会本部次長・ 障害者支援施設「リアン文京」総括施設長 |
||
| 鈴木 俊文 | 静岡県立大学短期大学部講師 | ||
| C「FKスーパービジョン-家族システム論による事例解析-」
定員になりましたので申込を締め切りました。 |
|||
| 福山 和女 | 日本福祉大学研究フェロー・ルーテル学院大学教授 | ||
| 田中千枝子 | 日本福祉大学スーパービジョン研究センター長・ 社会福祉学部教授 |
||
| D「提言―精神障害者の就労支援方法論の蓄積から―」 | |||
| 倉知 延章 | 九州産業大学教授 | ||
| 田中 尚樹 | 日本福祉大学社会福祉学部助教 | ||
| 大谷 京子 | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 | ||
| E「生活困窮自立支援の計画づくりと資源開発 -東近江市の実験」 |
|||
| 泉本 了 | 東近江市健康福祉部健康福祉政策課課長補佐 | ||
| 山口美知子 | 東近江市市民環境部森と水政策課課長補佐 | ||
| 平野 隆之 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | ||
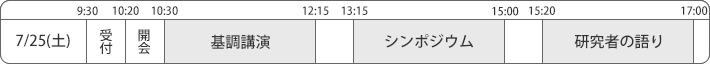

7/25(土):名古屋キャンパス北館8階
-基調講演・シンポジウム・研究者の語り
-基調講演・シンポジウム・研究者の語り
基調講演
10:30-12:15 |
「生活困窮者支援・政策が目指す資源開発 -社会的包摂の政策化過程の分析を踏まえて」 |
||
|---|---|---|---|
| 古都 賢一 | 独立行政法人国立病院機構副理事長 (前 厚生労働省 大臣官房審議官) 日本福祉大学客員教授 |
2000年の社会福祉基礎構造改革では、社会福祉の理念と制度の整理に関わり、生活保護行政を経て、生活困窮者支援制度の制定に関与された立場から、同制度の目指すものを論じます。その政策化の分析視点として、1つは「社会的援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」の報告が提起した「社会的包摂」の視点、もう1つは狭間の問題の解決を促進するための資源開発の視点から整理します。
シンポジウム
13:15-15:00 |
「 生活困窮者支援における資源開発の方法
-実践からの普遍化」 |
||
|---|---|---|---|
| 日置 真世 | よりそいホットライン全国コーディネーター・ 日本福祉大学アジア福祉社会開発研究センター客員研究所員 |
|
| 朝比奈 ミカ | 千葉県中核地域生活支援センターがじゅまる所長 | |
| コーディネーター | 平野 隆之 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 |
生活困窮者自立支援制度が成立する前から、現場ではその支援の必要に対応するための資源開発が取り組まれています。その現場に身を置き、相談支援をベースにしながらも、地域支援への展開、中間支援、ソーシャルアクションを通して地域に根差した資源開発を実践した経験に基づき、資源開発の方法を解説します。新刊の『相談支援員必携 事例でみる生活困窮者』(中央法規出版)が、その成果の1つとしてまとめられています。
研究者の語り
15:20-17:00 |
「私の行ってきた研究とその方法 -生活構造論から地域福祉研究へ」 |
||
|---|---|---|---|
| 野口 定久 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 |
私の社会福祉研究の契機は、学部と大学院において師事した籠山京先生と松崎粂太郎先生が主宰された「北海道和寒町の開拓農民の生活誌(ライフヒストリー)調査」(1950年-1975年)、そして、1976年の「川崎市南部におけ地域住民の生活実態調査(大都市の地域人間関係から疎外された人たちの生活実態)」でありました。これら高度経済成長期後の調査研究の経験は、今日、地域コミュニティにおいて貧困・格差問題の表出や「制度の狭間」に対するセーフティネットの構築(生活困窮者自立支援事業等)が求められているときに、「個別ニーズから政策提起、そして実践の組織化へ」というコミュニティ・ソーシャルワークの技術体系の展開にもつながっています。私の、これまでの住民生活実態調査による地域コミュニティ論を基盤とした生活構造・貧困研究から地域福祉・居住福祉研究への系譜を皆様にお伝えしたいと思います。
7/26(日):名古屋キャンパス北館 5・6・7・8階/南館401・601
-分科会
-分科会
9:30-16:00
A「量的研究(調査)法への誘い;“問い”の立て方から分析まで」
| 斉藤 雅茂 | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 |
「実践や研究を通じて貴重なデータを収集したにも関わらず、十分に活用できずに眠らせてしまった」経験はないでしょうか。その理由の1つとして「データ解析の手順や解析の仕方が分からない」ということが考えられます。本分科会では、実際の調査データを用いながら基本的なデータ解析の流れを体感して頂くことを目標に、問い(リサーチ・クエスチョン)の立て方から初級・中級者向けのデータ解析の方法、解析結果の報告までを演習形式でおこないます。現場で何らかのニーズ調査や実態調査などを予定されている方、学術研究につながるような量的調査の実施をお考えの方、計量的なデータ解析を用いた学会発表や学術論文の投稿を予定されている方など、多くの参加をお待ちしております。なお、パソコンの台数が限られておりますので、SPSSやSTATAなどの統計解析ソフトがインストールされているノートパソコンをお持ちの方はぜひご持参下さい。
B 「質的研究(調査)法への誘い-質的研究で実践現場のリアルが見えてくるⅡ-」
| 田中千枝子 | 日本福祉大学スーパービジョン研究センター長・ 社会福祉学部教授 |
|
| 山内 哲也 | 社会福祉法人武蔵野会本部次長・ 障害者支援施設「リアン文京」総括施設長 |
|
| 鈴木 俊文 | 静岡県立大学短期大学部講師 |
本分科会では、日本福祉大学大学院質的研究会が出版した「介護福祉・社会福祉の質的研究法-実践者のための現場研究(中央法規)」を活用し、質的調査を用いた現場研究の成り立ちを基礎的な枠組み・視点から解説していきます。本の内容に沿って話が進みますので、参加者は事前に本の購入をお願いします。
質的研究法の“系統的学び”として、今回の夏季大学院分科会を含め次のような「研修体系」を設定しています。6月14日に学びの入り口・整理として「質的研究法(研究事例)のショーケース」を実施し、続けて本分科会で概論講義と導入演習を体験します。そしてさらに具体的な質的研究(調査)法を、実際の事例を活用・体験できる10月31日・11月1日に2日間の後続研修会を予定しています。その際は各テーブルに1名のチューターが付き、皆さんの理解が進むように、質的研究(調査)の醍醐味が味わえるように、丁寧に進めていきます。研修プログラム体系全体の参加をお願いします。
| 後続研修会 | : | 質的研究研修会(第3回):『質的研究を体験する』 |
| 日時 | : | 10月31日・11月1日/日本福祉大学名古屋キャンパス |
C 「FKスーパービジョン-家族システム論による事例解析-」
定員になりましたので申込を締め切りました。
| 福山 和女 | 日本福祉大学研究フェロー・ルーテル学院大学教授 | |
| 田中千枝子 | 日本福祉大学スーパービジョン研究センター長・ 社会福祉学部教授 |
日本におけるスーパービジョンの母 D.デッソー先生の一番弟子で、永年日本のソーシャルワーク実践を見守り、指導されてこられた、本学研究フェローでもある福山和女先生のスーパービジョン演習です。根っからのシステム論者で、かつ家族療法研究のスペシャリストでもある先生が、家族システム論を用いて事例を解析する貴重な機会となります。
事例のテーマは「曖昧な喪失」です。喪失のウェットさとシステムのドライさ加減が事例の中でどのように結びつくのか、大いなる関心を持って参加されることを望みます。
D「提言―精神障害者の就労支援方法論の蓄積から―」
| 倉知 延章 | 九州産業大学教授 | |
| 田中 尚樹 | 日本福祉大学社会福祉学部助教 | |
| 大谷 京子 | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 |
精神障害者は、歴史的背景や、原因疾患の多様性や障害の固定されなさといった特性から、就労支援についての研究や実践は後発領域といえるでしょう。ところが近年、就職件数は年々増加しており、その支援対象も多様化し、対象者と企業双方への適切な支援方法論の確立が課題になっています。
本分科会では、精神保健福祉領域の就労支援について、先進事例を交えた現状と課題についての講演と、発達障害者支援から見出せる就労支援の課題についての報告を聞きます。それらを踏まえて、事例検討を受講者と共に行います。
E「生活困窮自立支援の計画づくりと資源開発-東近江市の実験」
| 泉本 了 | 東近江市健康福祉部健康福祉政策課課長補佐 | |
| 山口美知子 | 東近江市市民環境部森と水政策課課長補佐 | |
| 平野 隆之 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 |
生活困窮者自立支援制度の普及・円滑な運用において、自治体が主体となって取り組む計画づくりが不可欠な方法です。東近江市では、3年間のモデル事業を取り組みながら、2015年3月に「地域生活支援計画」として、それを打ち出しました。そのプロセスは、今回のテーマである出口プログラムの資源開発の模索や実験の過程でもありました。その過程に参加した3名のメンバーによるその過程の振り返りと計画を実行に移すための手段を検討します。
受講生の自治体の事例を交えることができれば、比較検討も可能となります。
16:00-17:00
分科会まとめ
分科会終了後会場を北館8階に移し、各分科会の成果を確認します。
主催:日本福祉大学福祉社会開発研究所
後援:日本福祉大学同窓会
| 【会場案内図】 | 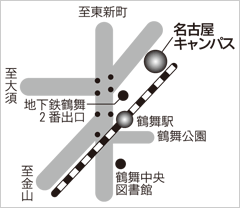 |
日本福祉大学 名古屋キャンパス
名古屋市中区千代田5-22-35
|
