
現場で生じる問題が複雑化しています。その現実を「つかむ」ために、社会福祉の理論をどう活用すべきなのか。研究方法を扱う本大学院ゼミナールでは、今回理論研究の方法をとりあげ、それを学ぶことを通じて、これまでの見方では捉えきれなかった現実を新たに「つかみ」なおす試みに挑戦します。
現代社会において求められる社会福祉理論とは何か、現実を「つかむ」という課題に研究書はどこまで対応できているのか、研究者は、どのように理論を用いて現実の問題をつかんできたのか、これらの問いを正面に据えた第9回セミナーとします。
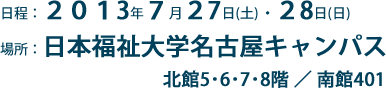
受付を終了いたしました。
1日目【7月27日(土)】
基調講演 |
|||
| 「社会福祉理論研究の方法と課題 −現代社会において求められている社会福祉理論とは−」 |
|||
|---|---|---|---|
| 岩崎 晋也 | 法政大学現代福祉学部教授 | ||
鼎 談 |
「理論と実践とを結ぶ「本を編む」」 | ||
| 岩崎 晋也 | 法政大学現代福祉学部教授 | ||
| 平野 隆之 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | ||
| 原田 正樹 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | ||
研究者の語り |
|||
| 「私の行ってきた研究とその方法 −著書「量産」の秘密」 |
|||
| 二木 立 | 日本福祉大学 学長 | ||
2日目【7月28日(日)】
分科会 |
A「量的研究(調査)法への誘い :データがゴミにならないために」 |
||
|---|---|---|---|
| 斉藤 雅茂 | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 | ||
| B「質的研究法への誘い −実践者のための質的研究法−」 ※定員になりましたので、受付を終了しました。 |
|||
| 田中千枝子 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | ||
| 山内 哲也 | 社会福祉法人武蔵野会本部次長 八王子実習所施設長 |
||
| 瀧澤 学 | 神奈川県リハビリテーション病院MSW 兼高次脳機能障害相談支援コーディネーター |
||
| C「学びながら実践するスーパービジョン 〜尾張スーパービジョン研究会方式〜」 |
|||
| 山口 みほ | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 | ||
| 野田 智子 | 尾張スーパービジョン研究会世話人代表 /愛知県厚生連江南厚生病院 地域医療福祉連携室 室長 |
||
| D「ソーシャルワーカーに求められるアセスメント力 ―研修プログラム開発研究―」 |
|||
| 大谷 京子 | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 | ||
| 吉田みゆき | 同朋大学社会福祉学部准教授 | ||
| 寺澤 法弘 | 日本福祉大学社会福祉学部助教 | ||
| E「震災被災地の個別・地域支援に関わる実践的研究」 | |||
| 児玉 善郎 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | ||
| 穂坂 光彦 | 日本福祉大学福祉経営学部教授 | ||
| 平野 隆之 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | ||

7/27(土):名古屋キャンパス北館8階
−基調講演・鼎談・研究者の語り
−基調講演・鼎談・研究者の語り
基調講演
10:30−12:00 |
「社会福祉理論研究の方法と課題 −現代社会において求められている社会福祉理論とは−」 |
||
|---|---|---|---|
| 岩崎 晋也 | 法政大学現代福祉学部教授 |
社会福祉理論、特に社会福祉原論は何のために存在するのでしょうか。ルーティンな実践を行っている人にとって、社会福祉原論への必要性はほとんどないかもしれません。しかし、社会福祉を取り巻く社会的情勢は常に動いており、現状に追従しているだけでは、進むべき道を見失うことがあります。時には目の前の課題だけでなく、全体を俯瞰するように見渡すことが必要となります。そうした時に、現状を分析し、進むべき道を示すのが、社会福祉原論の役割であるといえます。しかし近年、原論研究への関心は低い状況にあります。
本講演では、戦後の社会福祉学界における原論研究の動向を整理し、今後の課題を明らかにすることで原論研究への興味を喚起したいと思います。また、私自身が行ってきた理論研究を紹介し、どのような意図・方法で研究を行ってきたかについて述べることで、一つの理論研究の方法論を提示したいと思います。
鼎 談
13:00−15:00 |
「理論と実践とを結ぶ「本を編む」」 | ||
|---|---|---|---|
| 岩崎 晋也 | 法政大学現代福祉学部教授 | |
| 平野 隆之 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | |
| 原田 正樹 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 |
最近『舟を編む』の出版を契機として、本の編集プロセスが注目されています。研究書を編む際にも、実は一番楽しい時間は、この企画・編集段階なのです。われわれが編集した書籍を素材に、理論と実践(現場)を結ぶための編集のあり方を論じます。最近の有斐閣企画の「つかむシリーズ」や「リーディングス日本の社会福祉」の編み方を素材とします。
研究者の語り
15:20−17:00 |
「私の行ってきた研究とその方法 −著書「量産」の秘密」 |
||
|---|---|---|---|
| 二木 立 | 日本福祉大学 学長 |
私は、1973年に医学部を卒業した後、13年間臨床医を続ける傍ら、医療経済学等の勉強と研究を行い、1985年度に日本福祉大学に赴任しました。本学には28年間勤務し、本年4月、学長に就任しました。本学に赴任した直後に、「毎年1冊は著書を出版する」と決意し、28年間に23冊の著書(単著・共著等。編著は含まず)を出版し、ほぼ目標を達成しました。うち2冊では学会賞等を受賞しました。私の研究の視点と方法は、『医療経済・政策学の視点と研究方法』(勁草書房,2006)で詳しく紹介しました。本講義では、その後7年間に行った私の研究とその方法を紹介します。合わせて、コンスタントに論文を発表し、それらを速やかに単著にまとめる私の心構えとノウハウをお伝えします。
7/28(日):名古屋キャンパス北館 5・6・7・8階/南館401
−分科会
−分科会
9:30−15:30
A「量的研究(調査)法への誘い
:データがゴミにならないために」
| 斉藤 雅茂 | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 |
「とりあえず大規模な調査を実施してみたものの、結局、得られたデータは大して活用されずに眠らせてしまった」ということはないでしょうか。その対策として、本分科会では、まずは良いデータを集めることに焦点をあて、調査デザインと調査票の作成方法を取り上げます。現場で何らかのニーズ調査や実態調査などを予定されている方、学術研究につながる量的調査の実施をお考えの方など、多くの参加をお待ちしております。
また、本分科会の継続企画として、10月19日(土)にはパソコンを使った調査データの入力方法から簡単な集計作業までの演習を行います。定員17名で、今回の「量的研究法分科会」参加者を優先して受け付けます。
B 「質的研究法への誘い
−実践者のための質的研究法−」
※定員になりましたので、受付を終了しました。
| 田中千枝子 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | |
| 山内 哲也 | 社会福祉法人武蔵野会本部次長 八王子実習所施設長 | |
| 瀧澤 学 | 神奈川県リハビリテーション病院MSW 兼高次脳機能障害相談支援コーディネーター |
このたび質的研究(調査)法グループは、今まで取り組んできた「質的研究方法論」の研究をまとめた本を出版いたしました(中央法規:発行7月予定)。実践や臨床研究フィールドの第一線でがんばっていらっしゃる方々が、自分の成果をまとめたいと思ったときに役立つ本と自負しています。今回の分科会はその本を使い、実際の研究の成り立ちを具体的に解説しながら、質的研究のおもしろさを共有できる企画にしたいと考えています。
本の内容に沿って話が進みますので、前日(夏季大学院ゼミ初日)・当日(分科会当日)での本の購入は極力お願いしたいと思います。(当日は著者割引で販売する予定です)
またこの分科会では次の継続企画を予定しています。この企画にも参加されると、より具体的にリアリティーをもって研究の進め方が理解できます。各テーブルに1名のチューターがつきますので、疑問点はその場でおたずねください。
| 継続企画 | : | 「質的研究体験講座 〜フォーカスグループによる当事者の語り〜」 |
| 日時 | : | 10月13日(日)14日(祝)連日で行います。(場所:日本福祉大学名古屋キャンパス北館5階) |
C 「学びながら実践するスーパービジョン
〜尾張スーパービジョン研究会方式〜」
| 山口 みほ | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 | |
| 野田 智子 | 尾張スーパービジョン研究会世話人代表 /愛知県厚生連江南厚生病院 地域医療福祉連携室 室長 |
職場の部下や後輩への指導や業務の管理に不安を抱えている方、「スーパーバイザーを続ける自信が持てない」という方、地域の仲間とともに成長できる場を求めている方、福祉現場でのスーパービジョンの実際に関心がある方等を対象とした分科会です。スーパービジョンに関する基礎知識のレクチャーを行った後、実践例をもとに、スーパービジョンの実施方法と、スーパーバイザー同士が学びあう仕組みを演習方式で検討します。
参加された方が職場や地域で実施可能な方法のヒントを見つけられる場にしたいと考えています。
D「ソーシャルワーカーに求められるアセスメント力
―研修プログラム開発研究―」
| 大谷 京子 | 日本福祉大学社会福祉学部准教授 | |
| 吉田みゆき | 同朋大学社会福祉学部准教授 | |
| 寺澤 法弘 | 日本福祉大学社会福祉学部助教 |
前半は、「アセスメントプロセス」がソーシャルワークの中でどのように語られてきたか、ソーシャルワーカーはいかにアセスメントプロセスを遂行すべきとされているかを共有します。後半では、実際にエキスパートソーシャルワーカーが頭の中でどのような思考をしながら情報収集しているのか、初任者ソーシャルワーカーがどこで失敗しているのか、質的調査で明らかになったポイントを報告します。その上で最後に、精神保健福祉領域のソーシャルワーカーを想定した模擬研修ワークショップを体験していただきます。
研修プログラムの開発に関心のある方のご参加をお待ちしております。
E「震災被災地の個別・地域支援に関わる実践的研究」
| 児玉 善郎 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 | |
| 穂坂 光彦 | 日本福祉大学福祉経営学部教授 | |
| 平野 隆之 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 |
われわれは、「震災被災地における要援護者への個別・地域支援に関わる実践的研究」をテーマに、2012年度の一年間、震災被災地の「サポートセンター調査」を試みながら、制度外ニーズにどのように対応すべきなのか、それを担う実践の意義と持続可能性を考察してきました。それらの研究実践を報告するとともに、被災地に求められる研究方法や研究課題を整理します。
15:30−16:30
分科会まとめ
分科会終了後、会場を移し各分科会の成果を確認します。
主催:日本福祉大学福祉社会開発研究所
後援:日本福祉大学同窓会
| 【会場案内図】 | 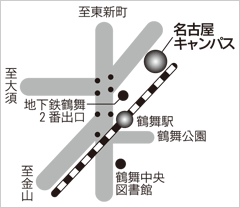 |
日本福祉大学 名古屋キャンパス
名古屋市中区千代田5-22-35
|
