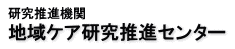
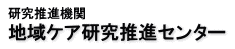 |
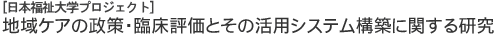 |
|
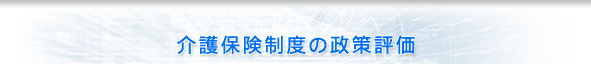
|
|||
|前のページに戻る| |
|
| 介護保険のアウトカムには、“客観的なもの”と“主観的なもの”が考えられます。日本福祉大学地域ケア研究推進センターでは、以下のようにアウトカム指標を開発しました。 |
| 「客観的指標」のアウトカム指標は、大きくは二つ作成しました。 |
| ● | 保険者が持つ業務データ(要介護認定データ)による2時点の変化数値 |
| “在宅支援”という政策目標に対応する在宅維持率(在宅でサービスを受けていたものが一年後も在宅でサービスを用いている率) | ||
| “自立支援”という政策目標に対応する要介護度の維持改善率(在宅でサービス受けていたものの要介護度が、一年後同じ要介護度である場合の「維持」と、要介護度が軽減した「改善」の合計数値) | ||
| ● | 訪問調査員あるいは担当のケアマネジャーによる介護状況の調査数値 |
| 介護放棄・虐待など「不適切な介護」の発生率。 | ||
| 要介護者・介護者の主観的な側面も評価すべきであると考え、「主観的指標」のアウトカム指標として採用しました。 |
| そのうち2003年度の介護費用適正化事業では、調査実施の容易性から介護者の主観的因子のみ評価しました。 |
| このうち「客観的指標」は次のような特徴から「簡易ベンチマーク」としました。 その特徴は |
| 1) | 保険者ならば既に持っているデジタル化されたデータを使うことで、多数の自治体で比較的「簡易にベンチマークすること」を可能にしたこと |
| 2) | 既存デジタルデータからでも作成可能な政策効果(アウトカム)指標を開発したこと |
| 3) | 全国で統一された方法で収集された情報(本学開発の介護保険給付分析ソフトの出力データ及び要介護認定データ)に基づく客観的な数字で表せる指標群であるため、自治体間比較が可能となり、各保険者の特徴や相対的な位置を客観的に示したこと |
| そして、地域ケア研究推進センターではその“簡易ベンチマーク”のアウトカム指標として、150指標を開発しました。その内訳は次の通りです。 |
| [地域特性 7指標] | 保険者おける人口構成等の基本的な特性を表す指標 |
| [対象 6指標] | 保険者における被保険者の状況を示す指標 |
| [投入 28指標] | 保険者が介護保険事業に投入している費用及びサービス基盤を示す指標 |
| [サービス利用状況 45指標] | 保険者における介護保険サービスの利用状況を示す指標 |
| [アウトカム 34指標] | 保険者における介護保険事業の効果を示す指標 |
| [効率 27指標] | 保険者において「効果」を得るためにどの程度の費用が「投入」されたかを示す指標 |
| [公正 7指標] | 保険者における保険給付の公平性を示す指標 |
| しかし簡易ベンチマークは、政策評価に必要な全ての側面の情報を持っているわけではありません。例えば、“介護状況”や“世帯類型”や“介護者の有無”、“要介護までになされた介護予防策の有無”などの情報は含まれず、十全にアウトカムを評価するものを用意できるものではありません。そこで、次のような追加調査による「詳細ベンチマーク」も併用すべく開発しました。 |
|
簡易ベンチマークでは、把握できないが介護保険政策を評価する上では重要な内容をとらえるために、3つの追加調査(「一般高齢者調査」、「介護状況調査」、「介護者調査」)を用いて、より詳細で多面的なベンチマーク指標群を開発し、これを「詳細ベンチマーク」としました。 これは、細かくは約400項目に上るものですが、保険者間比較に主に用いるコアとなる指標として、40指標を作成しました。 この詳細ベンチマークにより、例えば、“居宅サービス利用の多い保険者は、介護力の乏しい要介護者多い”こと、“在宅維持率が高い自治体の一部には、施設入所待機者が多い”事実などが見えてきました。 詳細ベンチマークの基になった3つの追加調査については、次の通りです。 |
|
目的は、介護予防事業の対象となるハイリスク者を把握すること、リスク者が他保険者よりも多いリスクを明らかにすることで、各保険者が優先して取り組むべき介護予防事業を明らかにすることです。また、長期的には追跡調査(コホート研究)の追跡前データとすることも目的とし、数年後に要介護認定を受けたものおよび死亡したものを把握することで、より科学的な方法で、健康寿命の喪失(要介護状態+死亡)の危険因子を明らかにすることが可能となります。 調査対象は、要介護認定を受けていない65歳以上の一般高齢者を対象にしたもので、各保険者5000人あるいは全員としました。2003年度の介護費用適正化事業では、対象者数59,622人で、回収数は32,891人(回収率55.2%)でした。 |
|
目的は、要介護者のおかれている状況を把握することです。 対象は2003年5月に在宅サービスを利用した方で、調査方法としては担当のケアマネジャーに記入を依頼しました。2003年度の介護費用適正化事業でこの介護状況調査の回収状況は、対象者数13,913人、回収数は11,653人分(回収率83.8%)でした。 主な調査内容は、介護の質(介護放棄、虐待を含む)、世帯状況、施設入所申し込みの有無、リハビリテーション前置の有無、痴呆診断を受けたか否かなどです。 |
|
目的は、介護保険の政策目標である「介護の社会化」により、介護者の負担軽減という成果があがっているか否かを検証し、より効果的なケア・マネジメントのあり方を明らかにすることです。 対象は介護状況調査と同じく2003年5月に在宅サービスを利用した者で、ケアマネジャーが調査票を留め置き、主介護者に記入してもらい郵送での返送としました。2003年度の介護費用適正化事業でこの介護者調査は、対象者数12、520人、回収数は6、386人分(回収率51.0%)でした。 主な内容は、介護サービスやケアプランへの介護者の満足度やその理由、行政への要望事項、介護負担感や主観的健康感、うつ(GDS)などです。 |
| ▲ このページのTOPに戻る |
| Copyright @ 2003 Nihon Fukushi University.All Rights Reserved. |