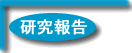
災害状況によっては子機→親機の通信が困難になる場合がある.親機は他の子機を介して,通信が困難な子機の安否情報を受信することができる(図4).
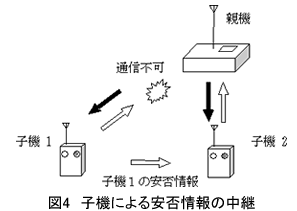
子機は他の子機の送信した安否情報をメモリ上に記録する.子機からの信号が親機まで届かなかった場合,それ以降の親機からのパケットには応答のなかった子機の安否情報を要求するデータが入れられる.子機は要求のあった情報についてデータを持っている場合,自らの安否情報を送信する際にそれらの情報も同時に送信する.
4.通信実験
14階建ビルの9階北側室内に親機を設置し,親機,子機を図5のように配置し通信実験を行った.実験では親機子機共に特定省電力無線機,空中線電力10mWでヘリカルホイップアンテナを使用した.
表1は親機−子機間の通信実験結果である.比較的電波の障害物が少ない所では200m以上の距離でも通信できた.建築物の谷間など込み入っているなど,通信状況の悪い場所に子機がある場合には送受信に失敗している.双方向で子機中継が可能なアルゴリズムを考案することで,子機が倒壊した建物の中にある場合にでも通信できる強固なシステムの開発が今後の課題である.

表1 安否情報送信実験結果
地点 |
親機からの距離(m) |
送信の成否 |
A |
80 |
○ |
B |
90 |
○ |
C |
95 |
○ |
D |
100
|
○ |
E |
115 |
○ |
F |
120 |
○ |
G |
145 |
× |
H |
160 |
○ |
I |
165 |
× |
J |
170 |
○ |
K |
200 |
○ |
L |
225 |
○ |
M |
240 |
× |
5.おわりに
本研究では災害発生直後における救助活動時の意思決定支援を目的として,住民の安否確認情報の収集システムを構築した.構築したシステムは有線設備が不要,携帯電話システムで問題となっている輻輳の問題がないなど,災害に対し頑強であり,操作性が良いという特徴を持つ.
2005年度には送信機数が数十台規模の実用化実験を行い,システムが設置されていることによる安心感や防災意識の向上などの効用について調査する予定である.
<参考文献>
[1]座間,細川,畑山,田村他:地震時の防災情報の創出とシステム化に関する研究,消研輯報第57号,(独)消防研究所,pp.5-9(2005)
[2]http://www.nttdocomo.co.jp/info/dengon/(2005/3)
[3]http://www.docomoeng-t.co.jp/goods/anpi.htm(2005/3)
[4]永井,北形,菅沼,白鳥:マルチエージェントに基づく大規模災害時における知人安否確認システム,電子情報通信学会技術研究報告,104(273)
,電子情報通信学会,pp.113−117(2004)
[5]仲上,吉越,小幡 編:新防災都市と環境創造−阪神・淡路大震災と21世紀の都市づくり−,法律文化社,pp.182−191 (1996)
[6]立命館大学震災復興プロジェクト 編:震災復興の政策科学,有斐閣,pp273−283 (1998)
[7]石川:震災時の安否確認システムについて,日本福祉大学情報社会科学部卒業論文(2003)
[8]大井:震災時における安否確認システム,日本福祉大学情報社会科学部卒業論文(2003)
| ←前ページ |