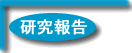
Arial書体は,比較的太い均一の幅の線で書字されており,細部の形状まで比較的認識しやすかったことが高い認識率をもたらす要因となっている.被験者の内省報告によると,Timesでは横線と縦線の線幅が異なっていたこと,Verdanaでは線幅が太すぎたことが正しい認識を阻害する要因となっていることが示唆された.また,Timesではフォント末端に「飾りひげ」による修飾がなされている.飾りひげは文字形状の強調に役立ち,触認識においても認識率向上に資すると期待されるが,正答率の結果,および,被験者の内観によれば,今回の実験状況においては飾りひげの効果は認められなかった.おそらく視覚認識用にデザインされた飾りひげでは,触覚認識用には微細すぎてその効果が現れなかったものと考えられる.今後は触覚認識に適したフォント末端処理のあり方を検討する必要がある.
また特定の文字種に対する認識率を検討すると,I,J,U,O,Sといった1画で鋭角的な変極点を持たない文字の認識率は非常に高く,どのフォント形状の条件でもほぼ100%の正当が得られた.一方,G,N,W,Xといった比較的複雑な形状の文字では認識率が低くなった.さらに,GとC,HとN,MとWなど,相互に混同されやすい文字のグループが存在することが明らかとなった.これらの結果は,触認識の際の空間分解能が視覚のそれと比して非常に低いものであることに起因すると考えられる.
幾何学図形を用いた触シンボルでは,フォントサイズが小さくなるほど認識率が低下し,24ポイント条件では正答率が50%を下回る(図3).しかしながら,線描画された図形や単純な塗りつぶし図形では,24ポイント条件においても(図形種による差異は存在するが)80%程度以上の正答率が得られている.同心配置や外環塗りつぶし図形など,複雑な図形配置のものは,96ポイントと図形全体を比較的大きくした条件においても,正答率はあまり向上しなかった.この結果から,☆など細部構造が図形認識の鍵となるような場合においては,単純に図形全体を拡大しても認識しやすさには貢献しないことが示唆された.触シンボル作成の際には,図形認識の手がかりが,図形全体に存在し,特定の細部構造には依存しない形状を使用することが望ましい.
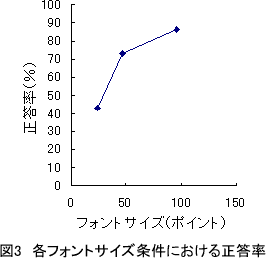
【実験3 触図呈示方法の検討】
・目的
本実験では,触図提示方法の新しい可能性を検討するために,PC上のグラフィカル情報をリアルタイムに触情報に変換することの可能な点図ディスプレイを用い,その情報表現能力のモニタリングを行った.
・モニタリング概要
・装置:実験装置としてKGS製点図ディスプレイ(DV−1)を用いた.DV−1は,PC画面上のグラフィカル情報を,24ドット×32ドットのピンドットの凹凸で表現することの可能な装置である.
・実験内容:点図ディスプレイ上にアルファベットの1文字を提示し,その文字が何であるかを遮眼した視力健常な男子大学生4名に回答させた.提示文字はTimes書体を元に,低空間分解能のディスプレイでも文字特徴を保持できるよう画像処理を施した(ダイレーション処理後細線化 図4).フォントサイズを6dotから16dotまで10水準設定し,文字種の判別が可能となる文字サイズの閾値を測定した.
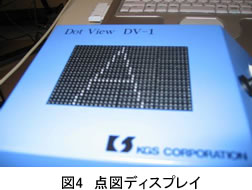
・結果:ロジスティック回帰モデルに基づく実験結果の近似を行い,75%の正答率が得られる文字サイズを判別閾値として採用した.文字種の違いによる差異は存在したが,ほぼ10ドット付近に判別閾値が存在することが明らかとなった.この結果は,点図ディスプレイを用いた場合には,実験2で検討した立体コピーによるアルファベットを用いた触シンボルの認識と比較して,よりフォントサイズが小さい条件において判別が可能なことを示している.点図ディスプレイの凹凸表現の明瞭さや事前の画像処理の効果など,複数の要因が関与していると考えられるが,本システムを触図表現に用いることが十分に可能であることが確認された.
【今後の展開】
今回の研究では,能動触における図形認知の基礎特性を幅広い条件で探索するために,遮眼した晴眼者を被験者として採用し,さまざまな知覚心理実験を行った.今後は,本研究で得られた基礎データに基づき,実際に触図コミュニケーションを必要としている中途失明者を被験者として,さらなる検討を重ね,触図作成のガイドラインを構築する.
【備考】
実験1の遂行に当たっては,日本福祉大学情報社会科学部の中川博明君の,実験2の遂行には日本福祉大学情報経営開発研究科の橋本洋平君,平林知樹君,水谷基人君,豊田道昭君の助力を得た.
| ←前ページ |