
知多半島が見えてくる本 トップページ > 産業観光 > 知多半島の産業観光地図 > 産業観光情報

利用料金、営業時間、休日などの詳細につきましては、このページ作成後に変更されていることがあります。
各施設のホームページまたはインターネットの検索でご確認の上、ご利用下さい。(2006.7.24現在)
|
|
|
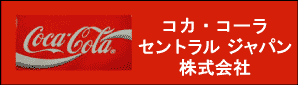 |
|
|
同行ガイドの説明により、最新鋭の機械と設備のもと、厳しい衛生・品質管理(1998年に同工場では品質管理の国際規格「ISO9002」を取得)を経て製品ができるまでの課程を無料見学できる。見学終了後にはお土産(コーラなど)がもらえるこもあり、ファミリーや遠足、社会見学などに人気のスポット。車椅子対応可。
|
|
|
|
|
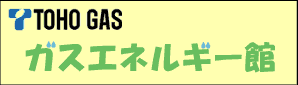 |
|
|
参加型実験やクイズ、映像などを通じて、大人から子どもまで楽しみながらガス等のエネルギーや環境について学ぶことができる。最上階には名古屋城や周辺の工業地帯が見渡せる展望室もある。コンパニオンによる案内制。入場無料。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
同社創立60周年を記念し、2000年3月にオープンした日本で唯一の鍛造専門の博物館。現在の最新技術についてはもちろんのこと、鎌倉時代、近江から大野谷(現在の常滑市、知多市の一部)に移り住み、農具の手入れのために周辺諸国へ出稼ぎに出たという「大野鍛冶」の歴史や技についても紹介し、「ものづくりの原点」を知ることができるのが特徴。高い専門性から、自動車関係業界を中心に海外からの視察も多い。入場無料。
|
|
|
|
|
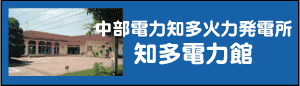 |
|
|
電気エネルギーに関するクイズ等、アミューズメントコーナーで遊びながら楽しく学べるだけでなく、事前申し込みをすれば、火力発電所施設の内部も見学することができる。施設内は車で移動するほど広大で、通常見ることはできない工場内のタービンや煙突の根元など、その巨大さには驚かされる。また、国際環境規格「ISO14001」を取得し、自然、環境にやさしい施設をコンセプトにしているのも特徴で、施設内にビオトープ(自然観察コーナー)を開設し、地域に解放するなど、ユニークな活動も展開している。入場無料。 |
|
|
|
|
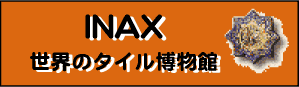 |
|
|
関連リンク:世界のタイル博物館ホームページ http://www.inax.co.jp/museum/ 常滑市に本社を置く(株)INAXが設立した、世界でも珍しいタイル専門の研究博物館。タイル研究家・故山本正之氏が収集した世界各地の色鮮やかなタイルが常設展示されているほか、2月から10月は企画展「やきもの新感覚シリーズ」、11月から翌年1月末は、館特別展を開催している。また、隣接地には、かつって常滑の街を象徴する土管を焼いていた窯をそのまま資料館にした「窯のある広場・資料館」、街の景観づくりへの提案をこめた「トイレパーク」、やきものやタイル絵つけなどを楽しめる「陶楽工房」もあり、常滑の地場産業である窯業をベースとした、ユニークな観光スポットとなっている。 |
|
|
|
|
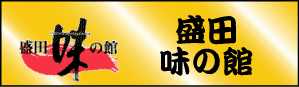 |
|
|
知多半島で古くから醸造業を営んできた(株)盛田が、160年前の醸造蔵を改造して1990年に設立。知多半島の伝統的地場産業である酒、味噌、醤油の製造プロセスがビデオで紹介される。15名以上の団体なら醸造蔵の内部見学も可能。(要予約)。昔ながらの風情漂う館内のショップでは、同社製品が販売されており、中にはここでしか手に入らないオリジナル商品もある。また、レストランも併設されており、同社の味噌などをベースにした食事を味わうこともできる。 |
|
|
|
|
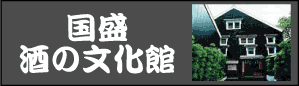 |
|
|
古くから醸造業で栄えた半田市にある中埜酒造(株)が、新工場稼動を機に、自社ブランドを冠して設立した、日本酒をテーマとしたユニークな企業博物館。建物は築200年の、江戸後期に建てられた酒蔵で、1972年までは実際に操業していた由緒あるもの。館内では展示説明や映像などで、日本酒に関わる知識や、先人の技について学ぶことができる。また、見学終了後は試飲ができるほか、他では入手できないオリジナル商品を購入することもできる。入場無料。 |
|
|
|
|
 |
|
|
半田市に本社を置く大手食品メーカー(株)ミツカンが1986年に設立した日本で唯一の酢の博物館。酢づくりの昔と今をわかりやすく紹介している。特に、同社の初代が200年前、それまでの米ではなく酒粕を原料とした「粕酢」の醸造に成功し、その酢が当時の海運の発達によって江戸へ運ばれ、江戸前ずしと酢が日本全国に広まったことを紹介するコーナーは興味深い。また、館周辺の運河沿いには昔の風情を残す酢蔵が並び、散策にも最適である。入場無料。 |
|
|
|
|
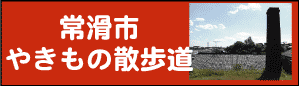 |
|
|
名鉄常滑駅からほど近い高台に、市の地場産業である常滑焼の窯元が集中したエリアがある。 |
|
Copyright(c) 2006 Nihon Fukushi University, The institute of Chitahanto Regional Studies.