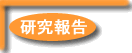 |
生物多様性に富み地域住民・都市住民が求める新たな里山管理モデルの構築 |
CE では, まず評価対象を表現し得る属性と水準を設定する. 通常は, 少人数で構成されるフォーカスグループを つくって属性と水準の選択について検討することが多い. 次に, 属性と水準の組み合わせで構成されたプロファイルと 呼ばれるものを複数つくる. ただし属性と水準の組み合わせで生じるプロファイル数が多い場合は, 直交配列を用いて プロファイルを削減することが望まれる. そしてこれらを組み合わせて二択や三択などの選択問題をつくり, どのプロファイル (選択肢) がもっとも好ましいか被験者に選んでもらう. 実際の CE の調査票ではこのような 選択問題を複数回連続させる. そして被験者全員の選択結果を従属変数とし, 属性の水準値を独立変数として, ランダム効用理論に基づく離散選択モデルにより統計的に解析する. この結果, 選択行動に対する各属性の 影響度合を定量化することが可能となる.
- 栗山浩一 (1998) 環境の価値と評価手法, 北海道大学図書刊行会
- 鷲田豊明 (1999) 環境評価入門, 剄草書房
里山保全モデルの構築 (大場)
大場はこれまでに都市施設と住居までの距離が住環境に及ぼす影響を住民の観点から評価し
(大場, 1999), 評価結果に基づいて意思決定を支援するシステムの構築 (柳本ら, 2000) を行ってきた.
また道路を例に, 施設の使用方法や調査対象施設の持つ特有の環境を含めた評価を行い, その上で
政策決定方法の提案, 政策提言を行ってきている (大場・仲上, 2001). このような手法は,
本研究に適応することが十分に可能である.
本年度は, 里山利用モデル構築のために, 文献調査, 岐阜県下呂市での森林調査を行い問題を整理し,
以下のことが分かった (大場).
人間の生活形態の変化が, 森林や農地などの里山の土地利用に大きな変化をもたらす. その一つが,
薪からガスや電気利用といった燃料の変化である. 薪を燃料としていた時代には, 周辺住民が里山の林を管理していた.
経済要因が里山の変遷に最も大きな影響を及ぼしていると考えられる. より収益の高い作物を求めることによる
森林から果樹園への変化, さらに, より高い収入を求めて離農することから果樹園などの農地が非管理林や荒地へと
変化を遂げている. 岐阜県下呂市の森林では杉や檜が植林されているが, 値段の安い外材の影響で木を育て切り出す
コストのほうが売り上げよりも高く, 間伐がなされない状態で放置された森林が多く見受けられるようになっている.
本年度は山の利用の要因と結果についてまとめた. 今後は, より詳細な因果関係について調査し, 里山利用モデルを
構築する予定である.
| ←前ページ |